|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
|
|
 |
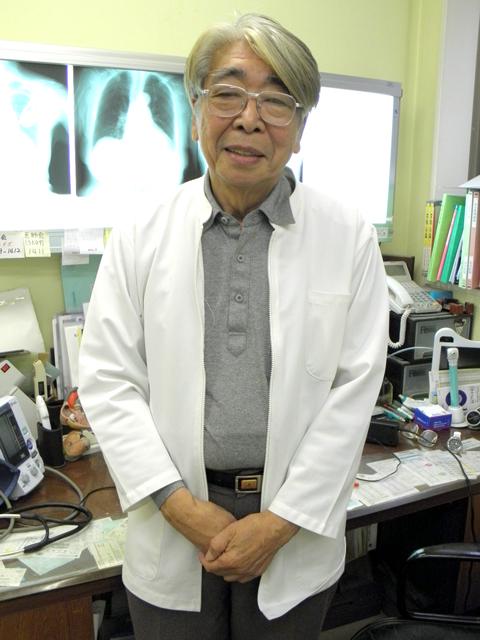
|
|
|
 |
 |
若月 透 院長
ワカツキ トオル
TORU WAKATSUKI |
|
 |
 |
若月医院 |
|
 |
 |
生年月日:1931年5月1日 |
|
 |
 |
出身地:東京都 |
|
 |
 |
血液型:O型 |
|
 |
 |
趣味・特技:音楽鑑賞、読書、碁 |
|
 |
 |
好きな本・愛読書:哲学書(最近ではサンデル教授の本も…)/ドストエフスキー、ロマン・ロラン、アンドレ・ジート |
|
 |
 |
好きな映画:ヨーロッパ映画 |
|
 |
 |
好きな言葉・座右の銘:初心忘るべからず |
|
 |
 |
好きな音楽・アーティスト:ワーグナー、マーラー/オペラ |
|
 |
 |
好きな場所・観光地:北海道 |
|
 |
 |
|
|
|
 |
 |
| ■医師を志されたキッカケをお聞かせください。 |
 |
父親が小児科をやっていたのを見て育ちましたから、誰に言われたからというのではなく、自然とこの道を選んだということだと思います。
東京医科大学に進み循環器を専門とし、ならびに内科一般を学び、1971年まで大学に勤めておりました。
その後、父が亡くなり、私が若月医院の跡を継いだのはその年のことです。40年近く(2010年現在)をこの地で医師として過ごしてきたということになります。 |
| ■診療の際に心掛けていることをお聞かせください。 |
 |
初心は皆さん、お持ちになっているものです。
医学に当てはめますと、まずきちんと予診をして、それから患者さんの診察に移り、1つ1つの検査をしっかりとおこなう。これがそうです。ですが、慣れてくると人間というのは省略することを覚えてしまうようになる。少しの手間を惜しむようになるものです。
必要性を考慮して、余分な手間を省くのがベテランということになるのかもしれませんが、その判断に『慣れ』という要素が入ってはならないのです。
「初心忘るべからず」。この言葉を私自身に対する警告と捉え、自分に対する戒めとして、常にこの言葉を意識するようにしています。 |
| ■「如何にして患者さんと向き合うか」についてお聞かせください。 |
 |
 電子カルテを実際に使っておられる先生方に聞きますと、患者さんとコミュニケーションをとるのが難しいという声をよく耳にします。データはパソコンの画面にありますから、どうしても視線がそちらに向いてしまい、結果として患者さんのお顔を十分に見てないということに陥りやすいと言われるのです。 電子カルテを実際に使っておられる先生方に聞きますと、患者さんとコミュニケーションをとるのが難しいという声をよく耳にします。データはパソコンの画面にありますから、どうしても視線がそちらに向いてしまい、結果として患者さんのお顔を十分に見てないということに陥りやすいと言われるのです。
いずれ誰もが電子カルテを導入することになりますが、如何にして患者さんにしっかり向き合うかという事が大きなテーマになってくると考えております。
当院は数年前(2010年現在)に改築をしたのですが、その際に救急医療に携わっていた息子の意見を取り入れ、診察室の中が全て見渡せるように余分な壁を取り払いました。
点滴を患者さんが受けているのも、何かの処置をしているのも全てが見える。自分の目が届くということは患者さんからも私を確認出来るということです。
患者さんとしっかりと向きあい、安心して治療を受けていただけるよう注力していきたいと思っております。 |
|
| ■最近の若い先生方について何か思われることはありますか? |
 |
私の世代と比較して、若い方の方が色々不足しているなどとは思っていません。むしろ知識や技術に関しては我々より遥かに深いものをお持ちだと思っております。
ただ1つだけ老婆心から申せば、どうしても専門に偏重してしまわれている傾向が見られるかと思います。
我々の時代とは医師の国家試験の難度が違いますから、医学以外の事柄に興味を持つということが難しいことは理解出来ます。私が学生の時は試験があっても当日の明け方まで小説を読んで、それでも何とかなってましたので(苦笑)。そんな時代と現在では比較にならない。
個人ではどうしようもない制度上の問題が大きいかと思いますが、一般知識があることによってより患者さんと近い距離で診察に臨めるという利点はあるかと思います。
ただ、お若い先生にお会いして、そういった点を何かご自分でお感じになり、いろいろなものを吸収されようとなさっている姿も拝見してもいますから、言わずともよいことなのかと思ってはいますが(笑)。 |
|
| ■最後に地域の皆様へメッセージをお願い致します。 |
 |
『プライマリ・ケア』とは患者さんが何らかの不調を感じて最初に医療に接する段階で、特定の病気だけを診るのではなく、その方の近くで何時でもどんな事でも相談に応じることの出来る医師、またはその医療体制を指します。
ただ範囲を広げて何でも出来るというのとは違います。ローレベルではなく、出来るだけハイレベルのスキルや知識を持って様々な患者さんの疾患に対応出来るようにすることが肝心なことです。
もう40年近く(2010年現在)、『プライマリ・ケア』を標榜して地域のかかりつけ医となるべく頑張ってまいりました。お身体に何らかの不調や不安を感じておられる方はどうぞお気軽にご相談ください。
息子と協力して、地域の皆様のどんなお悩みにも親身になって関わっていける病院でありたいと考えています。
※上記記事は2010.11に取材掲載したものです。
個人の主観的な評価や情報時間の経過による変化などがございます事をご了承ください。 |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|